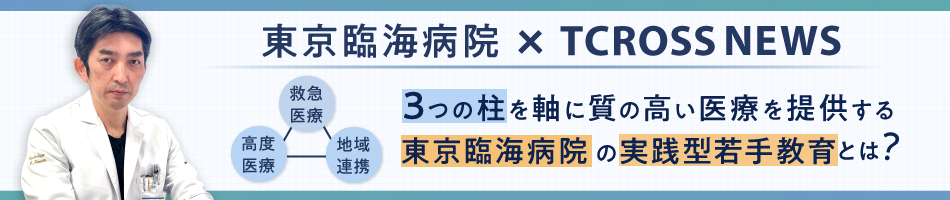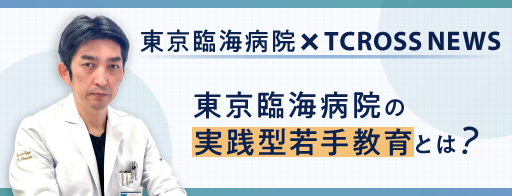
救急医療の推進、高度医療の提供、地域連携の構築を目指し、あらゆる心臓病に対応して治療を完結することを目標として診療に取り組む東京臨海病院循環器内科。 同院では24時間体制で急性心筋梗塞、急性心不全、重症不整脈などの救急疾患に対応し、最新の検査機器を用いて冠動脈インターベンションのみならず、不整脈アブレーション治療なども実施し、地域医療機関との情報公開を行い、地域の病院・医師との総合理解を深め、地域住民への質の高い医療の提供を目指している。
また、次世代を担う若手医師の人材育成に注力しており、日頃から循環器領域の最新動向やエビデンスなどについても院内で共通した認識を持っておくことを目指し、 TCROSS NEWSのグループ登録を導入した。今回、同院循環器内科の診療総部長である野本和幹氏に循環器のトレーニングプランや今回のグループプラン導入について伺った。
東京臨海病院では、若手医師を育成する活動としてルーティンに行われていることなどございますか。
東京臨海病院の循環器内科は、常勤スタッフと大学からの専攻医、ローテーターの初期研修医で構成されています。我々の施設では、循環器専門医研修、不整脈専門医研修、CVIT専門医研修が可能であり、 マニュアル式のプログラムはありませんが、実践を重視し、日々の臨床の中で指導を行っています。
若手医師には、一般診療もカテーテルインターベンションも臨床の中で多くの症例経験と専門医による指導が重要だと思っています。循環器内科医は一般診療において自ら診療にあたることも重要ですが、上級医の診療姿勢や患者への接遇を見て学ぶこと、 他職種との情報共有が大変重要であると私は考えています。当科では循環器内科チームとして1日2回のICU・病棟回診を循環器内科スタッフと病棟看護師で行っています。担当医の診療内容を複数医師で共有し、治療方針の決定や見直しなども複数の目でチェックしています。 看護師とも治療の方向性、患者さんへの病状説明を共有することで意思統一がされることを意識しています。
また週1回カテーテルカンファレンス(心臓外科医、放射線科スタッフ、看護師など)、週1回多職種病棟カンファレンス(医師、看護師、薬剤師、理学療法士、MSWなど)を行い情報共有しています。 さらに、カンファレンスでは、研修医に症例を提示してもらい、プレゼンのスキルアップができるようトレーニングしています。
東京臨海病院循環器内科のカテーテルインターベンションのトレーニングプランを教えてください。

当院には、大学からの専攻医が臨床経験を積むために派遣されて来るため、彼らのトレーニングを行なっています。 まずは1人で冠動脈造影検査を行えるように指導を行います。診断造影を200例程度経験してもらい、1人で問題なく実施できるようになればPCIの指導を行います。 読影も大変重要ですので、造影検査の後に読影も指導しています。
PCIを行える医師については、そのスキルに合わせて指導を行います。ほとんどのPCIは指導医が操作室でチェックし、指導・助言しながら行っています。 PCI前にストラテジーをディスカッションして手技に臨ませ、手技後に指導医から術者に内容についてフィードバックするようにしています。 CTOや分岐部病変の複雑な手技の場合は、事前に手技の手順を確認して指導医が横で確認しながら手技を進めます。 難易度の高い治療であっても、まずは担当医にできるところまでやってもらい、安全性を確認しながら難しければ指導医が介入するといった考えで指導しています。
また、新しいデバイス、初めて使うデバイスなどは、メーカーの協力を得て、実際に患者さんの治療にあたる前にハンズオントレーニングを行っています。
TCROSS NEWSのグループ登録をされた背景と活用方法について教えてください。

当院は大学と異なり、図書や文献検索などの教育ツールが弱いという状況が以前からあり、PCI雑誌購読や学会参加などの自己研鑽は個人に委ねられていました。 症例経験も重要ですが、その一方で、教育や知識、最新の医療技術・情報のアップデートは常に重要な分野であると考えています。 私は以前からTCROSS NEWSを利用していましたが、スタンダードプランでしたのでなかなか満足のいく情報を得ることができませんでした。
最近の私の考え方の中で後身の教育ということが重要なテーマとなってきています。自分のスキルアップも重要ですが、循環器内科チーム全体のスキルアップをすることで当院の診療レベルを上げ、 より良い医療を提供することができるのではないかと考えるようになりました。これは、医療安全の面からも重要なことであると思います。
その中でTCROSS NEWSの循環器内科チーム全員での利用を思いつきました。このサービスを利用するなら間違いなくプラチナプランがお得であると思います。 学会情報をリアルタイムで配信し、動画コンテンツなども充実しています。さらに無償でPCI LIVEなどを視聴できます。コロナ禍でなかなか学会にも参加できず、 Web配信の学会やLIVEが当たり前となった現代の医療に適したサービスだと思います。
現在の医療は非常に細分化され、多くの情報がネット上に溢れています。我々医師は限られた時間の中で、その中から自分に最適なものを見つける必要があります。 そのような信頼できる情報源を見つけることはとても困難ですが、TCROSS NEWSはその近道になると思います。
TCROSS NEWSは、個人の情報ツールとしてもちろん重要ですが、教育用のツールとしての価値があるのではないかと思います。導入後、循環器スタッフとは、「あのLIVEみた?」とか「今度あのLIVEがあるよ」など話をしています。教育用の利用法として、TCROSS NEWSコンテンツ内の手技や学会記事についてチーム内で共有することが有用ではないかと考えています。 特にPCIについては、動画のコンテンツが教育に最適であると思います。
若い先生方は新しいことを学ぶことを欲しておりますが、「学会会場に行くのはめんどくさい」、「雑誌を買うのはお金がもったいない」という価値観の医師も多く、このサービスが彼らにはちょうどよく、導入によってスタッフの知識欲を満たすことができるためモチベーションも上がりました。 今後は、ローテートする循環器を目指す初期研修医にもサービスを利用させることを考えています。
その他にも、スタッフの士気を高める方法として、情報共有ツールとしてiPad支給、チーム白衣支給などを行なっています。 コロナ禍の厳しい医療事情であり、スタッフのモチベーション維持は非常に重要な課題です。
今後、TCROSS NEWSに期待することを教えてください。
当科の不整脈チームからは、アブレーションや不整脈関連のコンテンツがもっと欲しいという要望がありましたので、今後は虚血領域に加えて、 これらの領域や循環器全般の情報も充実してもらうことを希望します。